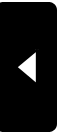2009年09月10日
BOUZ DC-1003
というわけで、この夏に買って当たりだったモノにこんなモノがあります。

BOUZ の「ドラッグチェッカー DC-1003」です。
ボートでの釣りで、以前はオモリを吊して、、、という話をしましたが、オモリを複数吊すのが面倒くさくて、結局、手動に戻っていました。
手動のアバウトな感じでも大抵は問題ないですが、やはりムラがある&イザという時に不安なのは確か。
しかも、ライン強度に対してどのぐらいなのか感覚だけではわからないので、そこも何となく思い切りフッキングできない一つの原因にはなっていたと思います。
で、たまたま買い物中に「あ、そうだ!」と気がついたので買ってみました、前から気になっていたこのドラグチェッカーを。
使って見た感想は、、、買って良かった!!
やはり目で「?kg」とわかるのは非常に分かり易い。
メインラインが 12lb で ドラグを 1/4 設定とすると 「12lb/4 = 3lb = 450gx3lb = 1350g」、、、とすぐに設定値はわかるので、あとはこのチェッカーで何度か調整してしまえばおしまい。
数字で見てわかっているので、「これで切れたらラインにキズがあったか、腕の問題だw」と、割り切れ、思い切りロッドワークができるようになりました(^^;
ただ、このドラグチェッカー、250g 以下は対応していません。
アジングの場合、フロロ 2lb を使うと、「900g/4 = 225g」となり、ドラグユルユルの場合や、もっと細いラインを使う場合はドラグチェッカーでは対応できません。
そこで、アジングでは、、、

やっぱりこっちを使う事にしてみましたw
いつもアジングをする場所のアベレージから考えて、1.5lb でも問題無さそうなので、「450x1.5/4/3.75=45号」となるので、まずは前後の 40g と 50g を用意。
今まではアジングもドラグは手動設定だったんですが、これからは毎回同じセッティングをできるようにやってみようかと思っています。

BOUZ の「ドラッグチェッカー DC-1003」です。
ボートでの釣りで、以前はオモリを吊して、、、という話をしましたが、オモリを複数吊すのが面倒くさくて、結局、手動に戻っていました。
手動のアバウトな感じでも大抵は問題ないですが、やはりムラがある&イザという時に不安なのは確か。
しかも、ライン強度に対してどのぐらいなのか感覚だけではわからないので、そこも何となく思い切りフッキングできない一つの原因にはなっていたと思います。
で、たまたま買い物中に「あ、そうだ!」と気がついたので買ってみました、前から気になっていたこのドラグチェッカーを。
使って見た感想は、、、買って良かった!!
やはり目で「?kg」とわかるのは非常に分かり易い。
メインラインが 12lb で ドラグを 1/4 設定とすると 「12lb/4 = 3lb = 450gx3lb = 1350g」、、、とすぐに設定値はわかるので、あとはこのチェッカーで何度か調整してしまえばおしまい。
数字で見てわかっているので、「これで切れたらラインにキズがあったか、腕の問題だw」と、割り切れ、思い切りロッドワークができるようになりました(^^;
ただ、このドラグチェッカー、250g 以下は対応していません。
アジングの場合、フロロ 2lb を使うと、「900g/4 = 225g」となり、ドラグユルユルの場合や、もっと細いラインを使う場合はドラグチェッカーでは対応できません。
そこで、アジングでは、、、

やっぱりこっちを使う事にしてみましたw
いつもアジングをする場所のアベレージから考えて、1.5lb でも問題無さそうなので、「450x1.5/4/3.75=45号」となるので、まずは前後の 40g と 50g を用意。
今まではアジングもドラグは手動設定だったんですが、これからは毎回同じセッティングをできるようにやってみようかと思っています。
タグ :DC-1003
2009年09月09日
水中集魚灯のその後
というわけで、例の水中集魚灯に電池を入れようとしたわけですよ。

ほうほう、まずは「保護ラバー」を外すのね。

っと、保護ラバーに手を掛け、回してみます。
、、、、ん゛、、、を゛、、、ま、回らん!!
買ってきたばかりなのに、いきなり壁にぶつかります(^^;
元々、太いので回し辛いのはあると思うんですが、それでもここまで回らないとは。。。
で、あれこれ見ていたら、、、

へー、長期間保管する時は若干ゆるめておくのね、、、と何気に現在の状態を見てみると、、、

あれ?これって、、、中途半端に閉まってない??
ガチガチでも無く、長期保管用にゆるめてるわけでもなく。。。
でも、いつ売れるかわからない事を考えると、最初から長期保管位置に設定されていても良いんじゃぁ?!
結局、あれこれ試すもビクともせず。。。
誰か開ける方法を教えてくださ~い!!(TーT

ほうほう、まずは「保護ラバー」を外すのね。

っと、保護ラバーに手を掛け、回してみます。
、、、、ん゛、、、を゛、、、ま、回らん!!
買ってきたばかりなのに、いきなり壁にぶつかります(^^;
元々、太いので回し辛いのはあると思うんですが、それでもここまで回らないとは。。。
で、あれこれ見ていたら、、、

へー、長期間保管する時は若干ゆるめておくのね、、、と何気に現在の状態を見てみると、、、

あれ?これって、、、中途半端に閉まってない??
ガチガチでも無く、長期保管用にゆるめてるわけでもなく。。。
でも、いつ売れるかわからない事を考えると、最初から長期保管位置に設定されていても良いんじゃぁ?!
結局、あれこれ試すもビクともせず。。。
誰か開ける方法を教えてくださ~い!!(TーT
2009年09月02日
キャプチャーネット&ワニグリップミニ
というわけで、りょう@表台。さんのマネっこ第二弾(^^;


ゴールデンミーンの「キャプチャーネット」と第一精工の「ワニグリップミニ」です。
キャプチャーネットは割と発売当初から人気の商品でしたが、個人的には自身のタモ事情に大きな不満があるわけでもなかったのでスルーしていました。
ワニグリップミニは、ボートでも使えるし、、、と大きい方を買ったんですが、今回用に買い足しです。
で、この2つ、、、別個に持っておくだけならば、、、まぁそれ程食指が動かなかったと思いますが、何とこの2つが合体w
タモのネットの根本とワニグリップミニをピンオンリールでくっつけると、、、

こんな感じでくっつけると、釣り上げたアジをタモでキャッチして、そのままワニグリップでキャッチできるというスグレもの。
最初から後ろにカールコードとカラビナが付いているので、ここにマグネット式のネットリリーサーを装着すると、さらに好感度アップ!!(^^;
という感じに、使っているのを横目で見ていて割と便利そうか?!と思ったので買ってみました。
まだ使っていないので、使うのが楽しみ!!
使ったらまたレポートします!


ゴールデンミーンの「キャプチャーネット」と第一精工の「ワニグリップミニ」です。
キャプチャーネットは割と発売当初から人気の商品でしたが、個人的には自身のタモ事情に大きな不満があるわけでもなかったのでスルーしていました。
ワニグリップミニは、ボートでも使えるし、、、と大きい方を買ったんですが、今回用に買い足しです。
で、この2つ、、、別個に持っておくだけならば、、、まぁそれ程食指が動かなかったと思いますが、何とこの2つが合体w
タモのネットの根本とワニグリップミニをピンオンリールでくっつけると、、、

こんな感じでくっつけると、釣り上げたアジをタモでキャッチして、そのままワニグリップでキャッチできるというスグレもの。
最初から後ろにカールコードとカラビナが付いているので、ここにマグネット式のネットリリーサーを装着すると、さらに好感度アップ!!(^^;
という感じに、使っているのを横目で見ていて割と便利そうか?!と思ったので買ってみました。
まだ使っていないので、使うのが楽しみ!!
使ったらまたレポートします!
2009年08月31日
パナソニック 水中集魚灯 BF-8952
というわけで、前回の釣行時に、りょう@表台。さんが幾つか面白いものを持っていたので早速マネっこ(^^;

パナソニックの水中集魚灯「BF-8952」です。
以前に富士灯器のガス式の集魚灯を持っていたんですが、ランニングコスト&メンテナンスの手間が比較的大きい上に実際にガスを燃やすので取り扱いに注意しないといけないので、買ってはみたもののあまり使わなくなっていました。
で、電池式の水中集魚灯ももちろん知っていたんですが、「電池よりもガスの方が光量的に性能が高いに違いない=効果が少ないハズ」という図式で、あまり食指は動きませんでした。
そんな中、りょう@表台。さんが、名古屋では割と使っている、という電池式の集魚ライトを持ってきて使ってくれました。
効果の程はまだハッキリと比べていないのでわかりませんが、小魚やイカの稚魚が集まってきたのは確か。
それを見ているだけでも割と面白かったので、買ってみようかな、、、と。
何と言ってもランニングコストは乾電池だけで、メンテナンスは基本的にフリー。
使い終わったら真水で洗って乾燥させるだけなのでお手軽。
何気に外箱を見ると、、、

アジ、メバル、イカ、、、何というベストマッチな対象魚(^^;
これからまた楽しみが増えました!!

パナソニックの水中集魚灯「BF-8952」です。
以前に富士灯器のガス式の集魚灯を持っていたんですが、ランニングコスト&メンテナンスの手間が比較的大きい上に実際にガスを燃やすので取り扱いに注意しないといけないので、買ってはみたもののあまり使わなくなっていました。
で、電池式の水中集魚灯ももちろん知っていたんですが、「電池よりもガスの方が光量的に性能が高いに違いない=効果が少ないハズ」という図式で、あまり食指は動きませんでした。
そんな中、りょう@表台。さんが、名古屋では割と使っている、という電池式の集魚ライトを持ってきて使ってくれました。
効果の程はまだハッキリと比べていないのでわかりませんが、小魚やイカの稚魚が集まってきたのは確か。
それを見ているだけでも割と面白かったので、買ってみようかな、、、と。
何と言ってもランニングコストは乾電池だけで、メンテナンスは基本的にフリー。
使い終わったら真水で洗って乾燥させるだけなのでお手軽。
何気に外箱を見ると、、、

アジ、メバル、イカ、、、何というベストマッチな対象魚(^^;
これからまた楽しみが増えました!!
2009年08月28日
第一精工 タックルキャリアー3518 続インプレ
というわけで、「タックルキャリアー3518」の続インプレです。
※ちなみに初回インプレの記事はこちら。
実際に何回か使ってみましたが、堤防などで使う分には非常に使い勝手が良かったです。
まず、心配していたショルダーベルトは必要ありませんでした。
メタルジグでも大量に入れない限りは大きさ的に重くならず、片手で十分持ち歩けます。
次は足の強度ですが、、、実は毎回足を伸ばすのを忘れて使ってました(^^;
気が付いた時に試しにロッドを入れた状態での倒れ易さをみてみましたが、思ったよりも倒れ易そうです。
立てておいたのがアジング用のウルトラライトセットだったのでそうでもありませんでしたが、エギングセットの場合は重量がある分、余計に倒れやすいかもしれません。
バッグの形状としては横幅が狭いので、多少荷物が入ったぐらいではロッドを立てた時の不安定感は変わらない気がしました。
なので、足はちゃんと伸ばした方が良いかも。
収納力は割とあるんですが、いかんせん深いので内部をうまく仕切るような箱なりケースが無いとスペースに結構無駄が生じます。
この辺りは 100均などで自分のスタイルにあったものを物色した方が早いかも。
真ん中のロッドホルダーにオートキングフレームのタモを立てる場合は結構きついです。
ネットを畳んだ状態でも左右のロッドホルダーに収納されているリールにネットが干渉してしまって、ネットを持ち上げる際にロッドまで抜けそうになって焦った事が数回(^^;
なので、ギャフで無い場合は、素直に手持ちの方が良さそう。
その分、真ん中のロッドホルダーに棒を立てて、そこにペットボトルホルダーやランタンを付けるのが一番便利な気がします。
個人的には堤防にてライトタックルで遊ぶにはかなり良い選択肢だと思います。
タモを手持ちにすれば、最大で3タックルまで持ち込めるし。
個人的に岸壁のアジングで使ってみた感じでは、買う前は60点で、使ってみて80点、という評価で、珍しく使った後の評価が高くなりました。
こうなると唯一の欠点は価格、、、ですね(^^;
※ちなみに初回インプレの記事はこちら。
実際に何回か使ってみましたが、堤防などで使う分には非常に使い勝手が良かったです。
まず、心配していたショルダーベルトは必要ありませんでした。
メタルジグでも大量に入れない限りは大きさ的に重くならず、片手で十分持ち歩けます。
次は足の強度ですが、、、実は毎回足を伸ばすのを忘れて使ってました(^^;
気が付いた時に試しにロッドを入れた状態での倒れ易さをみてみましたが、思ったよりも倒れ易そうです。
立てておいたのがアジング用のウルトラライトセットだったのでそうでもありませんでしたが、エギングセットの場合は重量がある分、余計に倒れやすいかもしれません。
バッグの形状としては横幅が狭いので、多少荷物が入ったぐらいではロッドを立てた時の不安定感は変わらない気がしました。
なので、足はちゃんと伸ばした方が良いかも。
収納力は割とあるんですが、いかんせん深いので内部をうまく仕切るような箱なりケースが無いとスペースに結構無駄が生じます。
この辺りは 100均などで自分のスタイルにあったものを物色した方が早いかも。
真ん中のロッドホルダーにオートキングフレームのタモを立てる場合は結構きついです。
ネットを畳んだ状態でも左右のロッドホルダーに収納されているリールにネットが干渉してしまって、ネットを持ち上げる際にロッドまで抜けそうになって焦った事が数回(^^;
なので、ギャフで無い場合は、素直に手持ちの方が良さそう。
その分、真ん中のロッドホルダーに棒を立てて、そこにペットボトルホルダーやランタンを付けるのが一番便利な気がします。
個人的には堤防にてライトタックルで遊ぶにはかなり良い選択肢だと思います。
タモを手持ちにすれば、最大で3タックルまで持ち込めるし。
個人的に岸壁のアジングで使ってみた感じでは、買う前は60点で、使ってみて80点、という評価で、珍しく使った後の評価が高くなりました。
こうなると唯一の欠点は価格、、、ですね(^^;
タグ :タックルキャリアー
2009年08月07日
第一精工 ワニグリップ
というわけで、意外と良かったアイテムの紹介です。

第一精工の「ワニグリップ」です。
少し前に naohareさん がアジングの時に「いいですよ~」と使っていたので気になってました。
ただ、メゴチバサミとラパラのフィッシュホルダーがあったので、さすがにそれほど変わらんだろう、、、と思いつつ使わせてもらったら全然使い易くてビックリ(^^;
何で使い易いか考えてみると、ポイントは2つ。
一つはメゴチばさみと比べて大きく開く口です。
挟む際は口の部分に魚を入れてから挟む事になりますが、口が狭いとビチビチ抵抗するアジくんはかなり挟み辛いです。
もう一つは挟む際の力が少なくて済む事。
これは「百聞は一見にしかず」系で、文章で読んだだけだと「メゴチバサミだってそんなに力はいらんだろう」と思ってしまいがちですが、実際に使うと全然違う事がわかります。
一番重要な事は、挟む際に使う力が弱いとその分、力加減をコントロールし易くなる、というところ。
指先で強く握るようだと、挟む力の微調整がやり辛くなります。
アジを挟んでエラを〆るには、胴体を挟む必要があります。(巨アジは頭で良さそうですが(^^;)
胴体が潰れるほどしっかり握ってしまうのであれば問題ないですが、できれば美味しく見栄え良く食べるにはあまり強くは握りたくない、、、という力加減を意識すると、メゴチバサミではアジの脱走率が結構高い(^^;
挟むのに失敗して足下でビチビチやっているのを追いかけている時間が結構切なかったんですが、ワニグリップだと一発でしっかりホールドできます。
ただ、口のギザギザが結構ギザギザしているので、魚体にどういう影響があるかは不明。
この辺りは使いながら様子をみたいと思います。
そんなわけで、来週は一週間の夏休み。
保育園も休みなので全開で釣り!!というわけにはいきませんが、そこそこあれこれできたらいいなぁ、、、と思っています。
基本的にはブログは更新しない予定ですが、気が向いたら書くかもしれません(^^;

第一精工の「ワニグリップ」です。
少し前に naohareさん がアジングの時に「いいですよ~」と使っていたので気になってました。
ただ、メゴチバサミとラパラのフィッシュホルダーがあったので、さすがにそれほど変わらんだろう、、、と思いつつ使わせてもらったら全然使い易くてビックリ(^^;
何で使い易いか考えてみると、ポイントは2つ。
一つはメゴチばさみと比べて大きく開く口です。
挟む際は口の部分に魚を入れてから挟む事になりますが、口が狭いとビチビチ抵抗するアジくんはかなり挟み辛いです。
もう一つは挟む際の力が少なくて済む事。
これは「百聞は一見にしかず」系で、文章で読んだだけだと「メゴチバサミだってそんなに力はいらんだろう」と思ってしまいがちですが、実際に使うと全然違う事がわかります。
一番重要な事は、挟む際に使う力が弱いとその分、力加減をコントロールし易くなる、というところ。
指先で強く握るようだと、挟む力の微調整がやり辛くなります。
アジを挟んでエラを〆るには、胴体を挟む必要があります。(巨アジは頭で良さそうですが(^^;)
胴体が潰れるほどしっかり握ってしまうのであれば問題ないですが、できれば美味しく見栄え良く食べるにはあまり強くは握りたくない、、、という力加減を意識すると、メゴチバサミではアジの脱走率が結構高い(^^;
挟むのに失敗して足下でビチビチやっているのを追いかけている時間が結構切なかったんですが、ワニグリップだと一発でしっかりホールドできます。
ただ、口のギザギザが結構ギザギザしているので、魚体にどういう影響があるかは不明。
この辺りは使いながら様子をみたいと思います。
そんなわけで、来週は一週間の夏休み。
保育園も休みなので全開で釣り!!というわけにはいきませんが、そこそこあれこれできたらいいなぁ、、、と思っています。
基本的にはブログは更新しない予定ですが、気が向いたら書くかもしれません(^^;
タグ :ワニグリップ
2009年08月05日
第一精工 タックルキャリアー3518
というわけで、雑誌で初めて見た時から期待していたアイテムが到着しました。

第一精工の「タックルキャリアー3518」です。
到着したのも束の間、気になっていた箇所を早速チェックです。
まず、持った感じはバッカンなので重さ的には気になりません。
持ち手の所は、、、

こんな感じになっていて、平面が合わさって丸いハンドルになります。
ただ、凹凸が若干堅めなので、まとめて握るだけでピッタリ合わさらないので、持つ時はグリップをちゃんと噛み合わせてから持った方が持ち易いです。
フタには、、、

こんな感じで両端にボタンがついていて、これをくっつけると半開き状態で固定できます。

ロッドホルダーの逆側サイドはこんな感じになっていて、、、

何かが引っ掛けられそうなループが2つあります。
元々の用途は不明。
で、気になるロッドホルダーは、、、

真ん中の径が若干大きく、広告写真のようにランディングギアが立てられるようになっています。
ポイントはホルダーの底が抜けていない事。
マルキューのタックルストレージのロッドホルダーは底が抜けているので、トラウトのようなリールフットからバットエンドまでが短いロッドならいざ知らず、ソルト用のロッドは持ち上げた時に深く入ってしまいます。
すると、移動後に地面に置く際に、突き抜けたバットが結構邪魔になって気を遣うので、そういった事は無いかな、と。
広告写真ではギャフが立ててありますが、これがタモだと恐らく左右のロッドと干渉すると思われます。
オートキングフレームを畳んだ状態ならば置けそうです。
ただ、ロッドホルダーに立ててあるロッドを近くに置いておくと、キャスト時に引っ掛かったり、フッキングミスで吹っ飛んできたリグが絡まったりとあまり良い事がないので、私の場合は極端に近くには置かない事が多いです。
逆にランディングギアは手元に置いておかないと「いざ!」という時に使えないので、そういった意味では、タックルキャリアにランディングギアを置くのは完全な移動時のみになりそうです。
そう考えると、リグ交換時などはランディングギアが真ん中のホルダーに入ってないので、取っ手が開いた状態になるので邪魔にはならないかな、、、と思ったり。
で、一番気になっていた足の部分です。

実際に見てみると割と太くてそこそこの強度がありそう。
広げるとこんな感じ。

この可動部の仕組みは、写真のように足の根本がバネで稼働するようになっていて、ホルダー側の角張った角を戻らないように、足の根本を固定するような感じになっています。

【バネを押さえた写真】

【バネを離した写真】

【バネを固定した写真】
強度は良さそうですが、問題は耐久力。
これは今後、使いながら見極めようと思います。
ここまで見てきた機能では大雑把に良さそうですが、若干物足りない点が二つ。
一つは、フタがコマセバッカン仕様である事。
現状だと、雨の日に内部に水が進入し易いと思うので、できればハードバッカンのフタのように、成型のフタをかぶせるようになっていて欲しかったなぁ、と。
もう一つはショルダーベルトが無い事。
いろいろと収納するとロッドやランディングギアの重さもあって、そこそこ重くなるはず。
そうすると腕だけで持ち歩くのはちょっと厳しそう。
それを考慮してバッカンサイズ自体が若干小さめなのかもしれないですが、気になるポイントではあります。
ちなみに容量的にはこんな感じ。

今は夏のアジングだけのつもりで購入しましたが、良さそうであれば冬のメバリングでも使おうと思っているので、今後、使い勝手をいろいろと検証したいと思っています。

第一精工の「タックルキャリアー3518」です。
到着したのも束の間、気になっていた箇所を早速チェックです。
まず、持った感じはバッカンなので重さ的には気になりません。
持ち手の所は、、、

こんな感じになっていて、平面が合わさって丸いハンドルになります。
ただ、凹凸が若干堅めなので、まとめて握るだけでピッタリ合わさらないので、持つ時はグリップをちゃんと噛み合わせてから持った方が持ち易いです。
フタには、、、

こんな感じで両端にボタンがついていて、これをくっつけると半開き状態で固定できます。

ロッドホルダーの逆側サイドはこんな感じになっていて、、、

何かが引っ掛けられそうなループが2つあります。
元々の用途は不明。
で、気になるロッドホルダーは、、、

真ん中の径が若干大きく、広告写真のようにランディングギアが立てられるようになっています。
ポイントはホルダーの底が抜けていない事。
マルキューのタックルストレージのロッドホルダーは底が抜けているので、トラウトのようなリールフットからバットエンドまでが短いロッドならいざ知らず、ソルト用のロッドは持ち上げた時に深く入ってしまいます。
すると、移動後に地面に置く際に、突き抜けたバットが結構邪魔になって気を遣うので、そういった事は無いかな、と。
広告写真ではギャフが立ててありますが、これがタモだと恐らく左右のロッドと干渉すると思われます。
オートキングフレームを畳んだ状態ならば置けそうです。
ただ、ロッドホルダーに立ててあるロッドを近くに置いておくと、キャスト時に引っ掛かったり、フッキングミスで吹っ飛んできたリグが絡まったりとあまり良い事がないので、私の場合は極端に近くには置かない事が多いです。
逆にランディングギアは手元に置いておかないと「いざ!」という時に使えないので、そういった意味では、タックルキャリアにランディングギアを置くのは完全な移動時のみになりそうです。
そう考えると、リグ交換時などはランディングギアが真ん中のホルダーに入ってないので、取っ手が開いた状態になるので邪魔にはならないかな、、、と思ったり。
で、一番気になっていた足の部分です。

実際に見てみると割と太くてそこそこの強度がありそう。
広げるとこんな感じ。

この可動部の仕組みは、写真のように足の根本がバネで稼働するようになっていて、ホルダー側の角張った角を戻らないように、足の根本を固定するような感じになっています。

【バネを押さえた写真】

【バネを離した写真】

【バネを固定した写真】
強度は良さそうですが、問題は耐久力。
これは今後、使いながら見極めようと思います。
ここまで見てきた機能では大雑把に良さそうですが、若干物足りない点が二つ。
一つは、フタがコマセバッカン仕様である事。
現状だと、雨の日に内部に水が進入し易いと思うので、できればハードバッカンのフタのように、成型のフタをかぶせるようになっていて欲しかったなぁ、と。
もう一つはショルダーベルトが無い事。
いろいろと収納するとロッドやランディングギアの重さもあって、そこそこ重くなるはず。
そうすると腕だけで持ち歩くのはちょっと厳しそう。
それを考慮してバッカンサイズ自体が若干小さめなのかもしれないですが、気になるポイントではあります。
ちなみに容量的にはこんな感じ。

今は夏のアジングだけのつもりで購入しましたが、良さそうであれば冬のメバリングでも使おうと思っているので、今後、使い勝手をいろいろと検証したいと思っています。
2009年07月17日
ウエダ Pro4EX XT-68FS-R
というわけで、今年の夏の為に予定していたタックルの最終品がようやく届きました。


ずっと気になっていたロッド、ウエダの「Pro4EX XT-68FS-R」です。
メバリングやアジングで上級者と思われる方々のタックルでよく聞くのはブリーデンの 3 兄弟とウエダのロッドでした。
ひとまず 3 兄弟を手に入れた後はメバリングでは気にならなかったんですが、最近ハマりつつあるアジングで気になり出しました。
いつものアジングでは大きく分けて 2 種類の釣り方をしています。
一つはシンカーを着底させるレオン氏提唱の方法。
もう一つはスイミング主体の方法。
前者にはもちろん 68strange を使いますが、後者には?!
何でもウエダのロッドはパツンパツンだけれども感度はバツグンと聞きます。
スイミング主体であれば感度の高い方が楽しいのかも、、、というのが一番の理由です。
2 番目の理由は軽量化(^^;
EXIST2004 と組み合わせれば、恐らくトータルで240g 前後となるので、ステラ+Wハンドルよりも軽くなります。
68strange+EXIST2004 よりも約 20g も軽量化できるので、いったいどうなってしまうのかと(^^;
で、感度を最大限に考えると一番短い TFL-64EX-R が良かったんですが、敢えて 68strange と比較するために XT-68FS-R にしました。
それにしても、届いたロッドに同梱されていた紙を見てちょっとドン引き。

常にドラグユルユルで、、、って、実際にスタッフがターゲットとなるクロダイやらマゴチを釣っている映像が見てみたくなりました。
これを見て思ったのは、、、
3 兄弟はレオン氏曰く「F1マシン」という事でしたが、これは F1マシンを一般人が日常レベルで使えるようにチューニングしたもので、あくまでも実用的な釣り用という位置付け。
ウエダの「F1マシン」はまさに本物の F1マシンで、いわゆるプロレーサーがサーキットで走る以外は保証対象外です、みたいな感じですね(^^;
何となく保証書の免責金額が 27,000円ぐらいするのも恐らくそういった事のあらわれなのかな、と。
つまり、店に卸す値段がそのまま免責金額??、、、という事は、免責金額にはウエダの儲け分がすでに上乗せされた金額という事??
職人が一本一本手作りで、、、という事なので、恐らく「1 ピースロッドの破損修理=新品ロッド」という事になると思います。
このように全面的に「破損注意!!」というロッドの割には、付属の竿袋は普通の形状、、、この紙を見た後では出し入れするだけで神経をすり減らされます。。。
まさにこれはF1マシンを注文したら、家にレッカー移動で届いた?!、、、みたいなw
こういった部分をみてしまうと、「F1マシン」という謳い文句に穿った見方をしてしまう、、、のは私だけ??(^^;
、、、と、あれこれ言いつつ、個人的には盛り上がりを見せているウエダロッドですが、本体以外に一つ問題が。
現在所有しているロッドケースの尺は 205cm。
XT-68FS-R は完全な 1ピースなので 205cm を超えます = 持ち運べません(^^;
そんなわけで、6.8ft が格納できるシマノのロッドケース RC-173G 215S も同時購入。

これは何気に良い買い物でした。
6.8ft がすっぽり入るので、68FS-R はそのまま、68strange はハンドルを付けたまま入ります。
内部のセンターにハンドルを入れる場所が一カ所あるので、そこに 74electro のハンドルを入れて、後は 74electro と 83deep を格納すれば全部入り(^^;
もちろんギリギリながら車にも入るサイズで大満足です。
6.8ft までの 1ピースをロッドケースに入れたい方にはオススメします!


ずっと気になっていたロッド、ウエダの「Pro4EX XT-68FS-R」です。
メバリングやアジングで上級者と思われる方々のタックルでよく聞くのはブリーデンの 3 兄弟とウエダのロッドでした。
ひとまず 3 兄弟を手に入れた後はメバリングでは気にならなかったんですが、最近ハマりつつあるアジングで気になり出しました。
いつものアジングでは大きく分けて 2 種類の釣り方をしています。
一つはシンカーを着底させるレオン氏提唱の方法。
もう一つはスイミング主体の方法。
前者にはもちろん 68strange を使いますが、後者には?!
何でもウエダのロッドはパツンパツンだけれども感度はバツグンと聞きます。
スイミング主体であれば感度の高い方が楽しいのかも、、、というのが一番の理由です。
2 番目の理由は軽量化(^^;
EXIST2004 と組み合わせれば、恐らくトータルで240g 前後となるので、ステラ+Wハンドルよりも軽くなります。
68strange+EXIST2004 よりも約 20g も軽量化できるので、いったいどうなってしまうのかと(^^;
で、感度を最大限に考えると一番短い TFL-64EX-R が良かったんですが、敢えて 68strange と比較するために XT-68FS-R にしました。
それにしても、届いたロッドに同梱されていた紙を見てちょっとドン引き。

常にドラグユルユルで、、、って、実際にスタッフがターゲットとなるクロダイやらマゴチを釣っている映像が見てみたくなりました。
これを見て思ったのは、、、
3 兄弟はレオン氏曰く「F1マシン」という事でしたが、これは F1マシンを一般人が日常レベルで使えるようにチューニングしたもので、あくまでも実用的な釣り用という位置付け。
ウエダの「F1マシン」はまさに本物の F1マシンで、いわゆるプロレーサーがサーキットで走る以外は保証対象外です、みたいな感じですね(^^;
何となく保証書の免責金額が 27,000円ぐらいするのも恐らくそういった事のあらわれなのかな、と。
つまり、店に卸す値段がそのまま免責金額??、、、という事は、免責金額にはウエダの儲け分がすでに上乗せされた金額という事??
職人が一本一本手作りで、、、という事なので、恐らく「1 ピースロッドの破損修理=新品ロッド」という事になると思います。
このように全面的に「破損注意!!」というロッドの割には、付属の竿袋は普通の形状、、、この紙を見た後では出し入れするだけで神経をすり減らされます。。。
まさにこれはF1マシンを注文したら、家にレッカー移動で届いた?!、、、みたいなw
こういった部分をみてしまうと、「F1マシン」という謳い文句に穿った見方をしてしまう、、、のは私だけ??(^^;
、、、と、あれこれ言いつつ、個人的には盛り上がりを見せているウエダロッドですが、本体以外に一つ問題が。
現在所有しているロッドケースの尺は 205cm。
XT-68FS-R は完全な 1ピースなので 205cm を超えます = 持ち運べません(^^;
そんなわけで、6.8ft が格納できるシマノのロッドケース RC-173G 215S も同時購入。

これは何気に良い買い物でした。
6.8ft がすっぽり入るので、68FS-R はそのまま、68strange はハンドルを付けたまま入ります。
内部のセンターにハンドルを入れる場所が一カ所あるので、そこに 74electro のハンドルを入れて、後は 74electro と 83deep を格納すれば全部入り(^^;
もちろんギリギリながら車にも入るサイズで大満足です。
6.8ft までの 1ピースをロッドケースに入れたい方にはオススメします!
2009年07月15日
ダイワ RCSB 100mmカーボンクランクハンドル
というわけで、先日購入した RYOGA。
シングルハンドルの回転半径が大きいのが何とかならないかしらん、、、と調べていたら、ハンドルがもう 10mm 短くできることが判明。
早速試してみるも、やっぱりもうちょっと短い方が、、、、と思ったので思い切って気になっていたダブルハンドルを試してみることにしました。
「RCSB 100mmカーボンクランクハンドル」と「パワーライトノブS」です。

これを組み立てて装着すると、、、

こんな感じになります。
回した感じは若干それでも大きいか??と思いましたが、ブリーデンのノーマルダブルハンドルを回した後にパワータイプを回したぐらいの違和感だったので、慣れかも、、、という変な納得(^^;
ダブルハンドルを交換していて思ったのは、スピニングと違って現場ですぐにハンドル変更できなさそうな構造が面倒くさいなぁ、と。
力の伝達の問題でしっかり造らないといけない部分ではあるので仕方が無いところですが、午前タチウオ、午後青物、みたいな時に船上で気軽に交換できると嬉しいなぁ、、、と思ったり。
ただ、巻き上げが軽いので、実はいつも釣っているぐらいの小~中型青物ではダブルハンドルでも問題無さそう??とも思ったり。
それはこれから使ってみて判断しようと思います。
そんな感じで、早速、写真のようにダブルハンドルをクルクルしながらラインを巻いていた訳ですが、なんだか違和感。
RYOGA は PE 2 号が 200m 巻ける仕様なんですが、何気に「ベイジギングセンサー20lb#1」を巻いてみたところ、かなりギリギリまででやっと全部巻けました。(適量だと 160m ぐらい?)
サンラインの「PEジガーHGライトスペシャル」の同号数と比べると明らかに極太。
もしかしてダイワの号数と lb って他と感覚が違う??(^^;
シングルハンドルの回転半径が大きいのが何とかならないかしらん、、、と調べていたら、ハンドルがもう 10mm 短くできることが判明。
早速試してみるも、やっぱりもうちょっと短い方が、、、、と思ったので思い切って気になっていたダブルハンドルを試してみることにしました。
「RCSB 100mmカーボンクランクハンドル」と「パワーライトノブS」です。

これを組み立てて装着すると、、、

こんな感じになります。
回した感じは若干それでも大きいか??と思いましたが、ブリーデンのノーマルダブルハンドルを回した後にパワータイプを回したぐらいの違和感だったので、慣れかも、、、という変な納得(^^;
ダブルハンドルを交換していて思ったのは、スピニングと違って現場ですぐにハンドル変更できなさそうな構造が面倒くさいなぁ、と。
力の伝達の問題でしっかり造らないといけない部分ではあるので仕方が無いところですが、午前タチウオ、午後青物、みたいな時に船上で気軽に交換できると嬉しいなぁ、、、と思ったり。
ただ、巻き上げが軽いので、実はいつも釣っているぐらいの小~中型青物ではダブルハンドルでも問題無さそう??とも思ったり。
それはこれから使ってみて判断しようと思います。
そんな感じで、早速、写真のようにダブルハンドルをクルクルしながらラインを巻いていた訳ですが、なんだか違和感。
RYOGA は PE 2 号が 200m 巻ける仕様なんですが、何気に「ベイジギングセンサー20lb#1」を巻いてみたところ、かなりギリギリまででやっと全部巻けました。(適量だと 160m ぐらい?)
サンラインの「PEジガーHGライトスペシャル」の同号数と比べると明らかに極太。
もしかしてダイワの号数と lb って他と感覚が違う??(^^;
2009年07月06日
オリムピック パラッジョ GSOPRS-62-GAME/3
というわけで、前回のチャーターメバリングが不発だった事もあり、何となくメバル熱が悶々と。
週末は隙を見つけて三浦にでも、、、と、久しぶりのマジ陸っぱりに若干ワクワク。
子供を早く寝かせて出撃!!、、、と、気が付いたら子供と一緒に爆睡してました(^^;
世の中の おとうさん はこんなもんです、よね?
そんな切ない週末でしたが、ようやく待っていたロッドが到着しました!!


オリムピックのジギングロッド、「PARAGGIO(パラッジョ GSOPRS-62-GAME/3)」です。
スペック的には、JIG:60~120g, LINE MAX(PE):2 号 という感じで、ライト寄り(ですよね?)にあたる近海ジギングロッドです。
フィッシングショーで実物を見てから待っていただけあって、やはり持った感じはバッチリ。
気持ち的には 6.8 ~ 7ft ぐらいあるとシイラのキャスティングとしても使えそうで嬉しいんですが、それはそれで本来のターゲットとは違うので仕方がないところ。
逆にジギング用としては「こんなのが欲しいなぁ」と想像していたものなので、08'ステラSW5000XG と一緒に今年のメインとして使っていこうと思います。
週末は隙を見つけて三浦にでも、、、と、久しぶりのマジ陸っぱりに若干ワクワク。
子供を早く寝かせて出撃!!、、、と、気が付いたら子供と一緒に爆睡してました(^^;
世の中の おとうさん はこんなもんです、よね?
そんな切ない週末でしたが、ようやく待っていたロッドが到着しました!!


オリムピックのジギングロッド、「PARAGGIO(パラッジョ GSOPRS-62-GAME/3)」です。
スペック的には、JIG:60~120g, LINE MAX(PE):2 号 という感じで、ライト寄り(ですよね?)にあたる近海ジギングロッドです。
フィッシングショーで実物を見てから待っていただけあって、やはり持った感じはバッチリ。
気持ち的には 6.8 ~ 7ft ぐらいあるとシイラのキャスティングとしても使えそうで嬉しいんですが、それはそれで本来のターゲットとは違うので仕方がないところ。
逆にジギング用としては「こんなのが欲しいなぁ」と想像していたものなので、08'ステラSW5000XG と一緒に今年のメインとして使っていこうと思います。
2009年07月03日
ダイワ RYOGA ベイジギング C2020PE-HL
というわけで、前回から引き続き NEW タックルのインプレです。
あれこれ迷っていたモノを前回のステラSWと一緒に買ってしまいました。
ダイワの「RYOGA C2020PE-HL」です。
以前は「ミリオネア・ベイエリアスペシャル 200BB」を使っていました。
(カタログや WEB を見たら記載されていなかったので型落ち?)
これは、船では巻きが長いので利き手でハンドルを回した方が、、、という情報を調べて購入したモノですが、実際、スピニングでは左で巻いているので右巻きに全然慣れず。
結果、慣れないものは使わない、使わないものは慣れない、、、というバッドスパイラルにハマってしまって出番が減っていました。
ある意味、初めてのベイトリールで若干トラウマ気味、、、みたいな(^^;
それを、あきらめるか/もう一度ベイトに挑戦してみるか、、、で迷っていたんですが、最終的にはダイワの DVDに思いっきり釣られました(爆



オプションパーツの「RCSB C2012PEスプール」と「RCS ライトジギングノブ」も併せて購入。
今回は迷わず左ハンドル仕様です。
で、早速、前回の釣行時に使ってみたわけですが、巻きの軽さにビビリました(^^;
フィッシングショーで触った時は確かに軽く感じたんですが、実戦でいつものように使って見るとさらに違いがわかってビックリ
ロッドでリフトすると結構潮の抵抗でジグが重いな、、、という時でも、ただ巻きすると「あれ?潮止まった?」とか「あれ?タチにジグ取られた?」みたいな(^^;
心配していた大きさですが、ロッドに装着してみるとそれほど大きく感じなかったです、、、ロッドは炎月ですがw
使ってみてポテンシャルに若干ゾクゾクするぐらいだったので、今後のメインとして使っていきたい!!と思えるリールでした。
ただ、タチウオのようにソフトなシャクリ主体で激しいシャクリを使わない場合は、ダブルハンドルの方が使い易いかなー、、、と感じました。
また、その巻きの軽さゆえに、潮流の変化を巻きで感じ辛い気もしたので、鯛ラバやインチクなどのタダ巻き中心の釣りで潮流の変化をリーリングで感じる事が必要になりそうな釣りには?!とも思いました。
鯛ラバもインチクもニワカなのであくまでも脳内イメージではありますが(^^;
ひとまずベイトのトラウマも払拭できそうだし、そうなるとベイトにあわせたロッドが、、、というループが怖い(^^;
あれこれ迷っていたモノを前回のステラSWと一緒に買ってしまいました。
ダイワの「RYOGA C2020PE-HL」です。
以前は「ミリオネア・ベイエリアスペシャル 200BB」を使っていました。
(カタログや WEB を見たら記載されていなかったので型落ち?)
これは、船では巻きが長いので利き手でハンドルを回した方が、、、という情報を調べて購入したモノですが、実際、スピニングでは左で巻いているので右巻きに全然慣れず。
結果、慣れないものは使わない、使わないものは慣れない、、、というバッドスパイラルにハマってしまって出番が減っていました。
ある意味、初めてのベイトリールで若干トラウマ気味、、、みたいな(^^;
それを、あきらめるか/もう一度ベイトに挑戦してみるか、、、で迷っていたんですが、最終的にはダイワの DVDに思いっきり釣られました(爆



オプションパーツの「RCSB C2012PEスプール」と「RCS ライトジギングノブ」も併せて購入。
今回は迷わず左ハンドル仕様です。
で、早速、前回の釣行時に使ってみたわけですが、巻きの軽さにビビリました(^^;
フィッシングショーで触った時は確かに軽く感じたんですが、実戦でいつものように使って見るとさらに違いがわかってビックリ
ロッドでリフトすると結構潮の抵抗でジグが重いな、、、という時でも、ただ巻きすると「あれ?潮止まった?」とか「あれ?タチにジグ取られた?」みたいな(^^;
心配していた大きさですが、ロッドに装着してみるとそれほど大きく感じなかったです、、、ロッドは炎月ですがw
使ってみてポテンシャルに若干ゾクゾクするぐらいだったので、今後のメインとして使っていきたい!!と思えるリールでした。
ただ、タチウオのようにソフトなシャクリ主体で激しいシャクリを使わない場合は、ダブルハンドルの方が使い易いかなー、、、と感じました。
また、その巻きの軽さゆえに、潮流の変化を巻きで感じ辛い気もしたので、鯛ラバやインチクなどのタダ巻き中心の釣りで潮流の変化をリーリングで感じる事が必要になりそうな釣りには?!とも思いました。
鯛ラバもインチクもニワカなのであくまでも脳内イメージではありますが(^^;
ひとまずベイトのトラウマも払拭できそうだし、そうなるとベイトにあわせたロッドが、、、というループが怖い(^^;
2009年07月01日
ST-BJ 651XHS と 08'ステラSW5000XG
というわけで、NEW タックルインプレです。
まずは、ジギング用ロッド。
ダイワの「ST-BJ 651XHS」です。

現在、タイラバで使っていたインフィートのベイジギングモデル 661XHS があるんですが、思ったより良かったので複数タックル用に近いものをもう一本買おうかと思っていました。
例えば、タチウオはフッキング率を上げようとするとフックが特殊になるので、そのまま青物用にするには交換の手間が掛かります。
そういった時に、タチウオ用と青物用の2タックルあれば、急な群れを逃す確率が減るというもの。
そんなわけで、候補に挙がったのは、ソルティガのベイジギングモデル「SG-BJ 64XHS」と、この「ST-BJ 651 XHS」でした。
ほぼ同じ仕様の 2 本ですが、最終的に若干軽くて若干長い ST-BJ 651XHS にしました。
で、使ってみた感想は、やっぱり使い易い。
ただ、タイラバと違ってジギングではシャクリが入ります。
このシャクッた時、長さのせいかリフト時にティップの入りによっては重めに感じました。
これはリールとの相性もあるような気がするので今後も気をつけて観察してみたいと思います。
お次はジギング&キャスティング用リール。
シマノの「08'ステラSW5000XG」です。


現在は小型&中型サイズの青物が主流なので、弱い力でのドラグ性能に威力を発揮する夢屋08'ステラSW センシティブドラグノブ(5000用)を付けてみました。
現在、02'ツインパ5000HG を持っているんですが、ターゲットを考えるとサイズ(重さ)的にはこれぐらいがシャクリ続けられる限度。
そういった意味で 5000 番にしたんですが、単なる 5000 番であれば 09'ツインパSW もあるのでそっちの方で間に合います。
ステラを選んだ理由はズバリ、ハンドル一回転当たりの巻き上げ量。
ちなみに、02'ツインパ5000HG は、94cm で、08'ステラSW5000XG は 105cm。
これだけであれば、恐らくツインパを買うか、スルーしていたと思うんですが、今回の目玉は何と 5000 番と 6000 番ではスプール互換があります。
ちなみに、02'ツインパでは 5000 番と 6000 番でボディが違ったので互換性はありませんでした。
対象となる 08'ステラ6000HG、スペック表では一巻き 103cm。
単純に計算すると、5000XG に 6000 番のスプールを装着すると、何と一巻き 111cm!!
明らかにスペックを見てニヤニヤしている私のようなターゲットを想像して、ニヤニヤしながらステラSWの 5000 番と 6000 番に互換性を持たせたような仕様(^^;
昨年の経験で大型が深い場所に居る時があっていつもの装備(ジグ40~60g)では厳しい時が何度かありました。
重いジグを深くて潮流が早い場所で巻き上げる、という事ができるように今年は調整してみたいと思います。
深いと言っても 70~100m ぐらいなので、ライトジギングとしては深い方、というぐらいではありますが(^^;
使ってみた感想は、回転滑らか!!
さすがステラの親分だけの事はあります。
ただ、重いジグで多少抵抗が加わると巻き始めに若干力が必要な時がありました。
ハイギアのXG なので宿命なのかもしれませんが、ロッドのティップとの相性もあるような気がするので、もうちょっと様子を見たいと思います。
そんなわけで、最終的には「パラッジョ + 08'ステラSW6000XG」という組み合わせを狙っています。
まだまだジギング初心者なので、使い易いタックルに巡り会うにはあれこれ試行錯誤が必要そうです。
とりあえず、、、早く青物来ておくれ~!!
まずは、ジギング用ロッド。
ダイワの「ST-BJ 651XHS」です。

現在、タイラバで使っていたインフィートのベイジギングモデル 661XHS があるんですが、思ったより良かったので複数タックル用に近いものをもう一本買おうかと思っていました。
例えば、タチウオはフッキング率を上げようとするとフックが特殊になるので、そのまま青物用にするには交換の手間が掛かります。
そういった時に、タチウオ用と青物用の2タックルあれば、急な群れを逃す確率が減るというもの。
そんなわけで、候補に挙がったのは、ソルティガのベイジギングモデル「SG-BJ 64XHS」と、この「ST-BJ 651 XHS」でした。
ほぼ同じ仕様の 2 本ですが、最終的に若干軽くて若干長い ST-BJ 651XHS にしました。
で、使ってみた感想は、やっぱり使い易い。
ただ、タイラバと違ってジギングではシャクリが入ります。
このシャクッた時、長さのせいかリフト時にティップの入りによっては重めに感じました。
これはリールとの相性もあるような気がするので今後も気をつけて観察してみたいと思います。
お次はジギング&キャスティング用リール。
シマノの「08'ステラSW5000XG」です。


現在は小型&中型サイズの青物が主流なので、弱い力でのドラグ性能に威力を発揮する夢屋08'ステラSW センシティブドラグノブ(5000用)を付けてみました。
現在、02'ツインパ5000HG を持っているんですが、ターゲットを考えるとサイズ(重さ)的にはこれぐらいがシャクリ続けられる限度。
そういった意味で 5000 番にしたんですが、単なる 5000 番であれば 09'ツインパSW もあるのでそっちの方で間に合います。
ステラを選んだ理由はズバリ、ハンドル一回転当たりの巻き上げ量。
ちなみに、02'ツインパ5000HG は、94cm で、08'ステラSW5000XG は 105cm。
これだけであれば、恐らくツインパを買うか、スルーしていたと思うんですが、今回の目玉は何と 5000 番と 6000 番ではスプール互換があります。
ちなみに、02'ツインパでは 5000 番と 6000 番でボディが違ったので互換性はありませんでした。
対象となる 08'ステラ6000HG、スペック表では一巻き 103cm。
単純に計算すると、5000XG に 6000 番のスプールを装着すると、何と一巻き 111cm!!
明らかにスペックを見てニヤニヤしている私のようなターゲットを想像して、ニヤニヤしながらステラSWの 5000 番と 6000 番に互換性を持たせたような仕様(^^;
昨年の経験で大型が深い場所に居る時があっていつもの装備(ジグ40~60g)では厳しい時が何度かありました。
重いジグを深くて潮流が早い場所で巻き上げる、という事ができるように今年は調整してみたいと思います。
深いと言っても 70~100m ぐらいなので、ライトジギングとしては深い方、というぐらいではありますが(^^;
使ってみた感想は、回転滑らか!!
さすがステラの親分だけの事はあります。
ただ、重いジグで多少抵抗が加わると巻き始めに若干力が必要な時がありました。
ハイギアのXG なので宿命なのかもしれませんが、ロッドのティップとの相性もあるような気がするので、もうちょっと様子を見たいと思います。
そんなわけで、最終的には「パラッジョ + 08'ステラSW6000XG」という組み合わせを狙っています。
まだまだジギング初心者なので、使い易いタックルに巡り会うにはあれこれ試行錯誤が必要そうです。
とりあえず、、、早く青物来ておくれ~!!
2009年03月25日
[ラパラ]スリングバッグと[BOIL]フローティングベスト
というわけで、前回の釣行時はいつもとは違う格好で望みました。
ポイントとなる装備は、やっと、、、というかアノ「スリングバッグ」です。
ひとまず”改造”はおいておいて、今あるタックルケースを突っ込んでの出撃です。
何と今回が初の実戦投入。
もちろん、ウェーディングベストではスリングバッグは動き辛いので、この日のために 2,3年前から用意していた BOIL のフローティングジャケットもあわせて投入です。
これら2つを使ってみた印象はなかなか良好。
フローティングベストの良い点は、背中に D管があるので、着ているだけでタモが背中に背負える事です。
スリングバッグを前後に持ち替えても干渉は少なかったので割と良い感じです。
ただ、浮力材が入っているので透湿性能は皆無。
この時期でも小磯を歩くだけで汗が滲んでくるのが難点といえば難点です。
今シーズンは最初で最後として、来シーズンは 12~2月限定ぐらいで出番がありそうです。
スリングバッグはコンパクトにまとめられるのであればかなり使い勝手は良さそうな感じでしたが、D管が無かったり、肩の辺りの小さい収納が使えなかったり、荷物が多いと微妙な点もありました。
メインストレージはワームやらプラグやらジグヘッドやらリーダーやらで満タンなので、それ以外で収納した道具は、、、
・・換えスプール2個
・・メジャー
・・プライヤー
・・フックシャープナー
・・予備ライト
・・タオル
・・ラインカッター
本当は持って行きたかったけど持って行かなかった道具は、、、
・・締め用ハサミ
・・キープバッグ
それと、メインストレージ上のベルトが装着されている大きな輪っかの部分をロッドホルダーとして使ってみましたが、手元でジグヘッドを結んだりする時にかなり邪魔になるので微妙な感じ。
ウェーディングジャケットではこれらの配置が全部決まるので、そういった意味ではもうちょっと使いこなしが必要そうです。
そうやってあれこれ考えていると、実は普通のメッセンジャータイプが良かったり?!とか思い出すとキリが無い今日この頃です(^^;
ポイントとなる装備は、やっと、、、というかアノ「スリングバッグ」です。
ひとまず”改造”はおいておいて、今あるタックルケースを突っ込んでの出撃です。
何と今回が初の実戦投入。
もちろん、ウェーディングベストではスリングバッグは動き辛いので、この日のために 2,3年前から用意していた BOIL のフローティングジャケットもあわせて投入です。
これら2つを使ってみた印象はなかなか良好。
フローティングベストの良い点は、背中に D管があるので、着ているだけでタモが背中に背負える事です。
スリングバッグを前後に持ち替えても干渉は少なかったので割と良い感じです。
ただ、浮力材が入っているので透湿性能は皆無。
この時期でも小磯を歩くだけで汗が滲んでくるのが難点といえば難点です。
今シーズンは最初で最後として、来シーズンは 12~2月限定ぐらいで出番がありそうです。
スリングバッグはコンパクトにまとめられるのであればかなり使い勝手は良さそうな感じでしたが、D管が無かったり、肩の辺りの小さい収納が使えなかったり、荷物が多いと微妙な点もありました。
メインストレージはワームやらプラグやらジグヘッドやらリーダーやらで満タンなので、それ以外で収納した道具は、、、
・・換えスプール2個
・・メジャー
・・プライヤー
・・フックシャープナー
・・予備ライト
・・タオル
・・ラインカッター
本当は持って行きたかったけど持って行かなかった道具は、、、
・・締め用ハサミ
・・キープバッグ
それと、メインストレージ上のベルトが装着されている大きな輪っかの部分をロッドホルダーとして使ってみましたが、手元でジグヘッドを結んだりする時にかなり邪魔になるので微妙な感じ。
ウェーディングジャケットではこれらの配置が全部決まるので、そういった意味ではもうちょっと使いこなしが必要そうです。
そうやってあれこれ考えていると、実は普通のメッセンジャータイプが良かったり?!とか思い出すとキリが無い今日この頃です(^^;
2007年09月07日
ミリオネア200BB と GAME 炎月 B661R
というわけで、夜な夜な ふと思いました。
GAME 炎月にミリオネア200BBが付かなかったりして!?(^^;
気になって早速取り付けてみると、、、


バッチリ付きました!
当たり前といえば当たり前ですが、ホッと一息。
試しに持ってグリグリしてみると、、、かなりフィット感高いですねぇ、ベイトタックルは。
ミリオネアも手で持つには丁度良い大きさで、気になっていたダブルハンドルも安定感を感じつつ巻き巻きできたので かなり満足。
唯一気になったのは、左手でのロッド操作が非常にやり辛かった事です。
以前は右ハンドル派でしたが、メバリングを機会に全て左ハンドルにしていました。
ここにきてまた右ハンドルとなると、、、結構感覚を忘れるものなのね(^^;
ワンピッチジャークのような巻きながらのアクションを試してみましたが、かなりギクシャクとして全然出来ませんでした~。
左ハンドルにも慣れたのですぐに慣れるとは思いますが、ちょっと意外な感覚でした。
こうなると状況によってハンドルの切り替えも、、、というのも頷けます。
GAME 炎月にミリオネア200BBが付かなかったりして!?(^^;
気になって早速取り付けてみると、、、


バッチリ付きました!
当たり前といえば当たり前ですが、ホッと一息。
試しに持ってグリグリしてみると、、、かなりフィット感高いですねぇ、ベイトタックルは。
ミリオネアも手で持つには丁度良い大きさで、気になっていたダブルハンドルも安定感を感じつつ巻き巻きできたので かなり満足。
唯一気になったのは、左手でのロッド操作が非常にやり辛かった事です。
以前は右ハンドル派でしたが、メバリングを機会に全て左ハンドルにしていました。
ここにきてまた右ハンドルとなると、、、結構感覚を忘れるものなのね(^^;
ワンピッチジャークのような巻きながらのアクションを試してみましたが、かなりギクシャクとして全然出来ませんでした~。
左ハンドルにも慣れたのですぐに慣れるとは思いますが、ちょっと意外な感覚でした。
こうなると状況によってハンドルの切り替えも、、、というのも頷けます。
2006年05月15日
ロッドとリールのバランス
今日は、リールとロッドのバランスの事に関して実験してみました。
通常、タックルを持った時の重量は、ロッドの重さとリールの重さになります。(ラインや仕掛けは除きます)
つまり、200g のロッドと 200g のリールでは、400g となります。
カタログではこのそれぞれの重さを見て、「重い」とか「軽い」を判断するわけですが、ここに意外な落とし穴があります。
ルアー釣りでは、キャストしては巻いて、キャストしては巻いて、、、の繰り返しで、ロッドをずっと振り続けていますよね。
この時、単純に総重量が軽いから良い、という事が言えない場合があります。
それは「持ち重り」です。
「持ち重り」とは、ロッドにリールをセッティングした時の重さの感じ方で、「持ち重りがする」というのは重心が悪い位置にある事を指します。
同じ 400g のタックルでも、重心がどこにあるかで明らかに持った時の重さ感が変わります。
それはロッドの振り易さに繋がり、魚から穂先に伝わる振動を感じる事にも影響を与えます。
では、どこに重心があるのが一番良いのか?
それは、リールフットの付け根の位置がベストだと思います。
何故かと言うと、少し重めの魚をロッドで抜き上げる時を想像すればわかると思います。
一般的に港湾で釣れる魚は重くてもスズキクラスの 数 kg ですよね。
ましてや小物では 1kg にも満たないものが大半です。
でも、抜きあげる時って凄く重く感じません?
釣った後に魚を持つとそんなに重く感じませんよね?
つまり、重さの重心が支点から離れた位置にあればあるほど重く感じます。
では、ロッドを持った時の支点とはどこでしょうか?
もちろん、手で持つところですよね。
持つ所といっても手の平全部では無くて、自分でリールの付いたロッドを持った時に、支点となって支えている指があると思います。
そこに重心があると一番軽く感じます。
自分の場合は、中指と薬指の間にリールフットを挟むので、中指が支点になります。
そこで、ここに重心を持ってくるにはどうしたらいいのかを今使っているタックル「GAME AR-C S706UL + 06'TWINPOWER Mg 2500SDH」で実験してみました。
まずは、普通にロッドにリールをセッティングした時の重心はこんな感じです。

つまり、リールフット側に重心を移動するには、バットエンド(竿尻)に重さを追加すればいい事になります。
(ちなみに AR-C シリーズでテレスコモデルと UL モデル以外は、専用のバランサーが取り付けられるようになっています)
そんなわけで、オモリを吊り下げられるように、マジックテープにフックが付いたものを使用しました。(ロッドが魚に持っていかれないようにする為のものです)
で、リールフット近辺に重心が移動するまでオモリを少しずつ足していくと、だいたい 30 号前後でバランスがとれました。

30 号と言うと、、、113g !!
つまり、ロッドとリールで 130g + 230g = 360g なのに、リールフットに 113g 足さないといけません。
ホントにこれで持ち重りが解消するのかしらん!?
と思ってしまいますが、持ってみるとビックリです。
確かに持っているんですが、重さの感じがまったく変わります。
とても 113g も重くなったとは思えません。
また、天秤の真ん中を持っているような感じになるので、ロッドティップ(穂先)に少しでも重さが加わったりする事に敏感になります。
そんなわけで、バットエンドに何かしらの重りを追加しようかと目論んでいます。
まずは板オモリでも巻こうかしらん。。。
というか、メーカーももうちょっと持ち重りを考慮してくれるとありがたいんだけどなぁ。
同じメーカーのロッドとリールでもバランスが取れないってのは、ちょっとおかしくないですか!?と思うのは私だけでしょうか?
せめて、AR-C のように別売りでもバランサーが付けられると嬉しいですね。
通常、タックルを持った時の重量は、ロッドの重さとリールの重さになります。(ラインや仕掛けは除きます)
つまり、200g のロッドと 200g のリールでは、400g となります。
カタログではこのそれぞれの重さを見て、「重い」とか「軽い」を判断するわけですが、ここに意外な落とし穴があります。
ルアー釣りでは、キャストしては巻いて、キャストしては巻いて、、、の繰り返しで、ロッドをずっと振り続けていますよね。
この時、単純に総重量が軽いから良い、という事が言えない場合があります。
それは「持ち重り」です。
「持ち重り」とは、ロッドにリールをセッティングした時の重さの感じ方で、「持ち重りがする」というのは重心が悪い位置にある事を指します。
同じ 400g のタックルでも、重心がどこにあるかで明らかに持った時の重さ感が変わります。
それはロッドの振り易さに繋がり、魚から穂先に伝わる振動を感じる事にも影響を与えます。
では、どこに重心があるのが一番良いのか?
それは、リールフットの付け根の位置がベストだと思います。
何故かと言うと、少し重めの魚をロッドで抜き上げる時を想像すればわかると思います。
一般的に港湾で釣れる魚は重くてもスズキクラスの 数 kg ですよね。
ましてや小物では 1kg にも満たないものが大半です。
でも、抜きあげる時って凄く重く感じません?
釣った後に魚を持つとそんなに重く感じませんよね?
つまり、重さの重心が支点から離れた位置にあればあるほど重く感じます。
では、ロッドを持った時の支点とはどこでしょうか?
もちろん、手で持つところですよね。
持つ所といっても手の平全部では無くて、自分でリールの付いたロッドを持った時に、支点となって支えている指があると思います。
そこに重心があると一番軽く感じます。
自分の場合は、中指と薬指の間にリールフットを挟むので、中指が支点になります。
そこで、ここに重心を持ってくるにはどうしたらいいのかを今使っているタックル「GAME AR-C S706UL + 06'TWINPOWER Mg 2500SDH」で実験してみました。
まずは、普通にロッドにリールをセッティングした時の重心はこんな感じです。

つまり、リールフット側に重心を移動するには、バットエンド(竿尻)に重さを追加すればいい事になります。
(ちなみに AR-C シリーズでテレスコモデルと UL モデル以外は、専用のバランサーが取り付けられるようになっています)
そんなわけで、オモリを吊り下げられるように、マジックテープにフックが付いたものを使用しました。(ロッドが魚に持っていかれないようにする為のものです)
で、リールフット近辺に重心が移動するまでオモリを少しずつ足していくと、だいたい 30 号前後でバランスがとれました。

30 号と言うと、、、113g !!
つまり、ロッドとリールで 130g + 230g = 360g なのに、リールフットに 113g 足さないといけません。
ホントにこれで持ち重りが解消するのかしらん!?
と思ってしまいますが、持ってみるとビックリです。
確かに持っているんですが、重さの感じがまったく変わります。
とても 113g も重くなったとは思えません。
また、天秤の真ん中を持っているような感じになるので、ロッドティップ(穂先)に少しでも重さが加わったりする事に敏感になります。
そんなわけで、バットエンドに何かしらの重りを追加しようかと目論んでいます。
まずは板オモリでも巻こうかしらん。。。
というか、メーカーももうちょっと持ち重りを考慮してくれるとありがたいんだけどなぁ。
同じメーカーのロッドとリールでもバランスが取れないってのは、ちょっとおかしくないですか!?と思うのは私だけでしょうか?
せめて、AR-C のように別売りでもバランサーが付けられると嬉しいですね。
2006年05月02日
タックル使用感
先日の釣りでは、何気に06'TWINPOWER Mg 2500SDHでの初釣りでした!
使用感は、、、キャストして巻くだけならば、05'バイオマスター2500Sとあまり変わらない気がします(^^;
20g 前後、軽くなっているはずではありますが、キャストするルアーが重くなった分、それほど軽くも感じませんでした。
結局は、お魚釣ってみないとわからないですねぇ、釣り具は。。。(TT
それと、実はもう一つ、お試ししたものがあります。
ダイワ LATEO 73LLです。

ルアーでのクロダイ釣りは、シャローが多いので割とお手軽なウキ釣りがやり辛い環境ではあります。
なので、連れがあまりにも暇を持て余すといけないので、一緒にルアーをやらせる為に買ってみました。
持った感じは軽くて長さも適当で凄く扱い易かったです。
そんなわけで連れは、ダイワ LATEO 73LL + 02アルテグラ2500 A-RB + サンライン クイン☆スター 600m クリアー 2.0 号直結、という装備でやってました。
結局、途中、軽いモモリが1回あったものの、あとはノントラブルで、飛距離もこっちの装備とあまり変わらなかったです。
値段も手頃だし、割といい買い物をしたかも。
PE でやっていたこっちは、強風と未熟な腕のおかげで、頻繁にガイドに絡んだり、モモったりしていたので、実は 2.0 号の直結が扱い易いのかなぁ、、、とも思ったりしました。
スキルを磨く為に PE を使うのも修行のうちだとは思いますが。。。(^^;
1 回、どうしても解けないモモリがでたので、予備のバイオマスターにしようかと思いましたが、これも経験だと思って強風の中で立ちながらFGノットを頑張って作りました。
すると、意外とできるもので、ちょっと自信になりました。
リーダーが太いとやり易いですねぇ、FGノット。
メバリングの時にチャレンジした事があるんですが、リーダーが細すぎてクニャクニャ曲がって凄く大変でした。
さて、GW中はどのタイミングで釣りに行くか迷うなぁ、、、半分は仕事しないといけないし。。。(TT
使用感は、、、キャストして巻くだけならば、05'バイオマスター2500Sとあまり変わらない気がします(^^;
20g 前後、軽くなっているはずではありますが、キャストするルアーが重くなった分、それほど軽くも感じませんでした。
結局は、お魚釣ってみないとわからないですねぇ、釣り具は。。。(TT
それと、実はもう一つ、お試ししたものがあります。
ダイワ LATEO 73LLです。

ルアーでのクロダイ釣りは、シャローが多いので割とお手軽なウキ釣りがやり辛い環境ではあります。
なので、連れがあまりにも暇を持て余すといけないので、一緒にルアーをやらせる為に買ってみました。
持った感じは軽くて長さも適当で凄く扱い易かったです。
そんなわけで連れは、ダイワ LATEO 73LL + 02アルテグラ2500 A-RB + サンライン クイン☆スター 600m クリアー 2.0 号直結、という装備でやってました。
結局、途中、軽いモモリが1回あったものの、あとはノントラブルで、飛距離もこっちの装備とあまり変わらなかったです。
値段も手頃だし、割といい買い物をしたかも。
PE でやっていたこっちは、強風と未熟な腕のおかげで、頻繁にガイドに絡んだり、モモったりしていたので、実は 2.0 号の直結が扱い易いのかなぁ、、、とも思ったりしました。
スキルを磨く為に PE を使うのも修行のうちだとは思いますが。。。(^^;
1 回、どうしても解けないモモリがでたので、予備のバイオマスターにしようかと思いましたが、これも経験だと思って強風の中で立ちながらFGノットを頑張って作りました。
すると、意外とできるもので、ちょっと自信になりました。
リーダーが太いとやり易いですねぇ、FGノット。
メバリングの時にチャレンジした事があるんですが、リーダーが細すぎてクニャクニャ曲がって凄く大変でした。
さて、GW中はどのタイミングで釣りに行くか迷うなぁ、、、半分は仕事しないといけないし。。。(TT
2006年04月28日
クロダイ用ルアーを調達!
そんなわけで、早速、クロダイ用のルアーを幾つか購入してみました。
まずは、ジャクソン R.A.POP です。

続いて FTEC のエス・フォー7です。

R.A.POP にイワシカラーが無かったので、これで間に合わせました。
最後にMリグ用のラパラ カウントダウン CD-7 です。

何故かこの色が他よりも安かったので買っておきました。
それにしても、一個ずつが高価なルアーを一度にこんなに購入したのは始めてなので、ちょっとドキドキです。
ポッパー 5 個 + CD-7 2 個で約 8,000 円。。。(^^;
あとは、気になっていた「SMOOTH 13lb 参考号数 0.8 号」も購入してみました。

で、リールに巻く為に開けてみると、、、何だかちょっと太い?
参考号数は 0.8 号だけれども、何だかGOSEN PEPET 1.5号ぐらい太い気が・・・。
と思いましたが、まぁ、0.8 号が間違って 1.0 号でも大丈夫かぁ、、、と思って、早速、06'TWINPOWER Mg 2500SDHに巻いてみたんですが、やっぱり問題が発生しました。
一般的にリールの糸巻き量としては、PE はフロロの約 80% ぐらいです。
つまり、06'TWINPOWER Mg 2500SDH は、フロロ 1.0 号が 140m 巻けるので、80 % だと 112m となります。
そう思って巻き始めたのに、何と 80m ぐらいしか巻けません。
もちろん、しっかりとテンションを掛けて巻いていたんですが、フチ一杯、ギリギリまで巻いても 90m ぐらいでした。
これを逆算すると、1.2 号から、1.5 号相当の太さです。
よく、コーティング剤がついているものは太くなっている、と聞きますが、こんなに太いのかしらん??
初めてなのでちょっと驚きです。
それと同時に、06'TWINPOWER Mg 2500SDH では出番が無さそうです(TT
C3000 のスプールでも購入したらまた考えます。
でも、バークレー FireLine XDS 16lb 114mを見る限り、それ程太くないように思えるんだよなぁ。
こっちは 1.0 号相当なので、SMOOTH よりは太いはずなんだけれども。。。
やっぱり SMOOTH が太すぎるのかしらん。
仕方が無いので、また何か探して巻いてみたいと思います。
まずは、ジャクソン R.A.POP です。

続いて FTEC のエス・フォー7です。

R.A.POP にイワシカラーが無かったので、これで間に合わせました。
最後にMリグ用のラパラ カウントダウン CD-7 です。

何故かこの色が他よりも安かったので買っておきました。
それにしても、一個ずつが高価なルアーを一度にこんなに購入したのは始めてなので、ちょっとドキドキです。
ポッパー 5 個 + CD-7 2 個で約 8,000 円。。。(^^;
あとは、気になっていた「SMOOTH 13lb 参考号数 0.8 号」も購入してみました。

で、リールに巻く為に開けてみると、、、何だかちょっと太い?
参考号数は 0.8 号だけれども、何だかGOSEN PEPET 1.5号ぐらい太い気が・・・。
と思いましたが、まぁ、0.8 号が間違って 1.0 号でも大丈夫かぁ、、、と思って、早速、06'TWINPOWER Mg 2500SDHに巻いてみたんですが、やっぱり問題が発生しました。
一般的にリールの糸巻き量としては、PE はフロロの約 80% ぐらいです。
つまり、06'TWINPOWER Mg 2500SDH は、フロロ 1.0 号が 140m 巻けるので、80 % だと 112m となります。
そう思って巻き始めたのに、何と 80m ぐらいしか巻けません。
もちろん、しっかりとテンションを掛けて巻いていたんですが、フチ一杯、ギリギリまで巻いても 90m ぐらいでした。
これを逆算すると、1.2 号から、1.5 号相当の太さです。
よく、コーティング剤がついているものは太くなっている、と聞きますが、こんなに太いのかしらん??
初めてなのでちょっと驚きです。
それと同時に、06'TWINPOWER Mg 2500SDH では出番が無さそうです(TT
C3000 のスプールでも購入したらまた考えます。
でも、バークレー FireLine XDS 16lb 114mを見る限り、それ程太くないように思えるんだよなぁ。
こっちは 1.0 号相当なので、SMOOTH よりは太いはずなんだけれども。。。
やっぱり SMOOTH が太すぎるのかしらん。
仕方が無いので、また何か探して巻いてみたいと思います。
2006年01月17日
軽量に勝るものはなし?
先日の話題の通り、

ダイワ 月下美人・ソルティスト ST-RF862X
これを注文したわけですが、気になっている事が一つあります。
それは重さです。
現在使っているロッドINFEET RF68が 110g で、リール05バイオマスター2500Sが 240g です。
ダブルハンドルなので多少重くなっているとして、240 + 110 + α = 350g + α ですね。
で、今回注文した月下美人・ソルティスト ST-RF862Xが、130g。
すると、240 + 130 + α = 370g + α となり、20g 重くなります。
この前にどうしようか迷った STX-RF 73-SVF か STX-RF 74S-SVFは 約 88 g。
また、ダイワのこれにちょうどいいぐらいのリールダイワ ソルティスト 月下美人 2004やルビアス2004は、約 200g。
つまり、88 + 200 = 288g となります。
その差、370 - 288 = 82 g。
これを重いと見るか、軽いと見るかは人によると思いますが、オモリの 22 号が 82.5g という事を考えると、結構な差になるかなぁ、と思いつつ、一瞬ながらルビアス2004の値段をチェックしてみたりして…(^^;
もし、これを組み合わせると、200 + 130 = 330g。
つまり、現在使っているタックルよりも長くなる上に軽くなるんですね~。
バランス的な持ち重りもあるので一概には言えませんが、やっぱり軽い方がいいなぁ、と思うのです。
そういった事を脳内で妄想し始めると…
月下美人・ソルティスト ST-RF862X を買う。
↓
楽しむ
↓
ルビアス2004を衝動買いする。
↓
軽さに味をしめる。
↓
気が付くとSTX-RF 74S-SVFを注文している。
という感じかしらん??(^^;

ダイワ 月下美人・ソルティスト ST-RF862X
これを注文したわけですが、気になっている事が一つあります。
それは重さです。
現在使っているロッドINFEET RF68が 110g で、リール05バイオマスター2500Sが 240g です。
ダブルハンドルなので多少重くなっているとして、240 + 110 + α = 350g + α ですね。
で、今回注文した月下美人・ソルティスト ST-RF862Xが、130g。
すると、240 + 130 + α = 370g + α となり、20g 重くなります。
この前にどうしようか迷った STX-RF 73-SVF か STX-RF 74S-SVFは 約 88 g。
また、ダイワのこれにちょうどいいぐらいのリールダイワ ソルティスト 月下美人 2004やルビアス2004は、約 200g。
つまり、88 + 200 = 288g となります。
その差、370 - 288 = 82 g。
これを重いと見るか、軽いと見るかは人によると思いますが、オモリの 22 号が 82.5g という事を考えると、結構な差になるかなぁ、と思いつつ、一瞬ながらルビアス2004の値段をチェックしてみたりして…(^^;
もし、これを組み合わせると、200 + 130 = 330g。
つまり、現在使っているタックルよりも長くなる上に軽くなるんですね~。
バランス的な持ち重りもあるので一概には言えませんが、やっぱり軽い方がいいなぁ、と思うのです。
そういった事を脳内で妄想し始めると…
月下美人・ソルティスト ST-RF862X を買う。
↓
楽しむ
↓
ルビアス2004を衝動買いする。
↓
軽さに味をしめる。
↓
気が付くとSTX-RF 74S-SVFを注文している。
という感じかしらん??(^^;